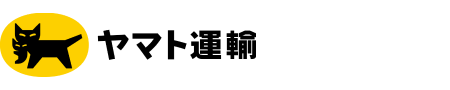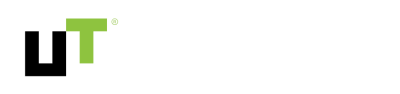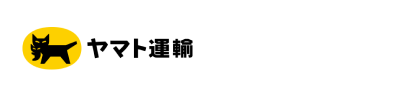ヤマトグループは2019年に創業100年目を迎え、2021年4月からこれまで機能ごとに展開していた事業会社をヤマト運輸に統合。
新しいヤマト運輸として再出発し、常に進化を遂げています。
同社では、お客様ニーズの多様化による「物流」に求められる重要性と柔軟性を実現するために、顧客接点の改革に取り組んでいます。コールセンターを顧客からの声を社内へフィードバックする第二の顧客接点の場として重要視しており、具体的には(①集荷 ②再配達 ③その他)3つのお問い合わせ種別に対応しています。
この3つのお問い合わせ種別の内、以下のようにAiCallを導入することで、お客様のマイナス体験を減らし、結果として満足度向上に つなげています。
① 集荷:2020年11月に法人顧客の集荷依頼でLINE WORKS AiCallの導入を行い、2021年4月には個人でも対応を開始
③ その他:2022年11月から「その他」のお問い合わせの一部でも導入を開始
本事例のポイント
-2020年11月に法人のお客様からの集荷依頼でLINE WORKS AiCallを導入、その後、個人のお客様へ
対応を拡大
-2022年11月からは「その他」のお問い合わせの一部でも導入を開始
-集荷依頼の約8割をLINE WORKS AiCallで対応
-お問い合わせ内容データの自動蓄積によりファクトデータ分析が可能となり、お客様ニーズを把握した効果的・効率的な打ち手を検討し実現が可能に
「お客様の声の代弁者」になる部門だからこそ、お客様が利用しやすい環境を整えることが大切
ヤマト運輸様が考える全体のCXの思想を教えてください。
田口さん :
皆さんが日頃接するセールスドライバーがお客様との接点の多くを占めますが、サービス利用においてのお困りごとに多く触れるのはコールセンターで、そのお客様の声を社内へ伝える「代弁者」という役割を担っています。
そのため、第二の顧客接点の場として重要視しています。
我々のコールセンターは全国からの電話を受け付けているため、地域・年齢に関係なく様々な方への対応ができるようチャネルの多様化を図ってきました。しかし、その一方で、運用がやや複雑になってきたという課題を抱えています。
今後はそれらをより磨いていくフェーズだと思っています。
更なる磨きをされていく中で、AIやデジタルへ期待していることや向き合い方について、お考えを教えてください。
田口さん :
まず、デジタルに関しては、今までFAQやチャットボットなどでよくあるお問い合わせに対応してきました。今は少し複雑なお問い合わせ内容でもAIを活用し、人が補助をすることで、より充実したサービスの提供を行うようにしています。
具体的に言うと、FAQやチャットボットなどでお問い合わせ対応を完結させることがゴールではなく、AIがお問い合わせ内容を事前に整理することで、お客様をオペレータにスムーズにつなげ、少しでも待ち時間を短くすることが大切だと考えています。
最短でお困りごとが解決できることで、お客様のマイナス体験を減らし、結果として満足度向上に繋がるのではないかと思っています。

AI活用によって、EX(従業員満足度)への貢献と、データによる次の打ち手をクリアにする
「CX」という言葉がキーワードになりつつも、コールセンターで働かれている方々にもスムーズなオペレーションを手助けしてくれるAIという存在は、きちんと貢献できているのでしょうか。
田口さん :
今までは、あらゆるお問い合わせをお電話でいただいていたため、回答の難易度に差がありました。
そのため、お問い合わせ内容によっては回答までにお時間をいただいてしまい、すぐに対応できないことがコールセンターで働く社員にも負担となっていました。
そうした課題に対し、AIの助けを借りながら、社員の働き方を含めて再設計することで、お客様にとっては満足度向上、社員にとっては働きやすい環境を実現していると思っています。
AI活用で、思わぬ副産物もあった、とお聞きしました。そのあたりもぜひ教えてください。
伊東さん :
AIを導入したことで、お問い合わせの履歴をデータとして蓄積することができます。これまでは、具体的なニーズを人の手だけでは整理しきれていなかった部分がありましたが、AIは自動的にデータを蓄積してくれるため、お客様のニーズを「ファクトデータ」として体系的に社内で把握することができるようになりました。
そのデータを分析し、どのようなニーズから対応すればお客様にとってより良い体験に繋がるのかを軸に、解決策を決められるため、非常に効果的・効率的にPDCAを回せられています。

集荷依頼の約8割をLINE WORKS AiCallで対応
2020年11月に法人のお客様からの集荷依頼にLINE WORKS AiCallの導入を行っていただきましたが、その時の背景などを改めて教えてください。
伊東さん :
2020年は新型コロナウイルス感染症の拡大により、ECの利用が増加した影響で、これまで以上にお問い合わせを多くいただくようになったため、本格的に導入の検討を開始しました。
特に最初に導入した法人のお客様からの集荷依頼に関しては、これまで有人のコールセンターに電話1つで集荷依頼が出来ていたというユーザー体験を崩さず、いかにスムーズにAIへ移行・活用していくか、という点を重視して取り組みました。
集荷依頼にAIを導入してから約2年経過しました。導入後の経過と成果はいかがでしょうか。
伊東さん :
現在ではコールセンターにいただくお問い合わせの約8割がLINE WORKS AiCallを経由してAIで対応しています。
また、ご希望のお客様にはAIが受付した内容をLINEメッセージで送信しており、テキストでも内容を確認することができるため、「便利!」という嬉しいお声もいただいています。

そうしたお声をいただけるのは、我々としても非常に嬉しいです。
続いて2022年11月に「その他」のお問い合わせの一部もLINE WORKS AiCallを導入いただきました。
そちらの導入背景なども教えてください。
伊東さん :
先ほどの『AIは自動的にお問い合わせ内容を蓄積するため、お客様のニーズを「ファクトデータ」として体系的に社内で把握することができた』という話と繋がっていきます。
蓄積したデータを見てみると、お客様からのお問い合わせ内容についても分類分けして把握できるようになりました。
特に「その他」のお問い合わせは、受電の際に確認する内容も多く、有人オペレータで対応すると対応品質にばらつきが出てしまうこともありました。
そこで、ある程度対応方法が決まっているお問い合わせであれば、LINE WORKS AiCallは相性がいいのではないかと思い、導入の検討を開始しました。
まさに、「データがファクトとなり、次の打ち手を効果的・効率的に行える事例」ですね。この導入を進める際のエピソードや効果などはいかがでしょうか。
伊東さん :
このシナリオを設計する際にかなり苦戦しましたが、LINE WORKS側からユーザー視点の助言を多くいただけたのは、大変ありがたかったです。
細かな言い回しや分かりにくいと感じる部分も丁寧にアドバイスいただきました。
そうしたシナリオ設計の甲斐もあり、順調に稼働しております。
「次の運び方をつくる」社会的インフラ企業だからこそ、あらゆる人に寄り添うコールセンターを
LINE WORKS AiCallの導入やデータ活用を効果的・効率的に進めていただいているヤマト運輸様ですが、今後取り組んでみたいことや今見えている解決したい課題などありますでしょうか。
田口さん :
昨今、お客様ニーズの多様化に合わせて、輸送サービスの種類も多様化しています。
今後は、お客様に提供しているサービスを整理・細分化し、できるだけシンプルな対応を心掛け、そのために精緻な設計を行っていくことが必要と考えています。
また、配送状況は地域の天候に大きく左右されるため、そうしたイレギュラー時に「配送エリア×天候」のようなイメージで、天候による交通状況などの情報を迅速に反映し、よりリアルで柔軟な対応ができるようになるとよいなと思います。
今回、インタビューをしていて強く感じたヤマト運輸様の「顧客視点」。
お客様とのコミュニケーションの将来・未来像に関しての展望を教えてください。
田口さん :
新型コロナウイルス感染症の影響や国際情勢の変化などにより、全産業のEC化が急速に進み、ライフスタイルやビジネスの環境が大きく変化しています。
そのため、コールセンターはよりお客様視点で充実したサポートを効果的・効率的に行う必要があると考えています。
また、高齢化がさらに進む日本においては、高齢の方への配慮も必要です。
デジタルやAIをうまく活用しつつ、高齢の方にもスムーズにお使いいただけるようなAI応対を企業として進めていきたいと考えています。その中で、直接お電話でお話されたいお客様のニーズもきちんと満たしながら、最適なコミュニケーションツールを今後も検討していきます。
LINE WORKS AiCallの4つの導入理由
-顧客満足度と社員の労働環境の向上を同時実現が可能
-2022年11月からは「その他」のお問い合わせの一部でも導入を開始
-顧客ニーズをデータ化することで、課題解決の効率的なPDCAが実現
-複雑なシナリオ設計を含め、手厚い導入サポート
※掲載している内容(製品名含む)、所属やお役職は取材を実施した2023年5月当時のものです。